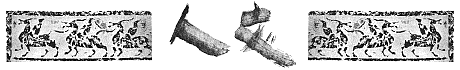
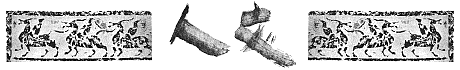
| 最新 | 講演会 | 研究所 | 研究活動 | 図書室 | 出版物 | アーカイブ | 目次 |
| 報告書 | 紀要 | 所報 | (第五三号 2006) |
| 随想 | 夏期講座 | 開所記念 | 退職記念 | 彙報 | 共同研究 | うちそと | 書いたもの | 目次 |
| 宇佐美齊 |
| 人文科学研究所所報「人文」第五三号 2006年6月30日発行 | |
退職記念講演(2005年度) |
|
詩を読む・語る・訳す |
|
宇 佐 美 齊 |
|
|
「詩に註釈は必要か」、という問いを発することから始めたい。私が専攻する象徴主義以降のフランス近代・現代詩のある種の難解さということに関連させて考えてみると、この問いはとりわけ切実である。詩が分かる、分からないという問題に関して言えば、例えば「分からない」ということの意味が、テクストと読者とが出会いを失したか、あるいはどのような火花をも散らすことなく終ってしまった、ということであるのならば、これにわざわざ註をつけていわば頭脳的に「分からせよう」とすること自体が、そもそも無意味だろう。たとえ難解であると感じられたにせよ、初めに詩の一行、あるいは片言隻語に引っ掛かりを覚え、あるいはなぜかは分らないけれども不思議な魅力を覚えた読者が、そこから少しずつ独自に作品ないし当該詩人の世界へと導かれる糸口を見い出してゆくのであれば、註釈などというものはほんらい不要のはずである。 とりあえず次のような答を今ここに提出してみたい。「基本的には不要である。ただし読者の理解を助けたり深めたりするための、最小限の語註、語釈、そして文体論的な説明はあってもいい。ただしそれらは読者の自由裁量権を侵害するものであってはならない。あくまでも控えめに、節度あるものを心掛けるべきである」、と。かつて私は当研究所の共同研究の成果報告書「ボードレール『悪の花』註釈」(多田道太郎編、一九八六年刊、一九八九年再刊)のあとがきに、こんな言葉を記したが、この考えは今も変わらない。 「ひとりの詩人がみずからの生と引き換えに残した彫心鏤骨のことばを、後世の人間があれこれ詮議して註釈を加える―、考えてみれば大それた企てである。漢詩人・阿藤伯海は、『諳んじてのち之を論ずるは善し、論ぜず之を楽しむは更に善し』と述べた。この教訓を肝に銘じたうえで、なおかつ論ずべき何ほどのものが残されているか、註釈者の節度と誠実さが要求されるところであろう」。 |
|
|
ところですぐれた詩人が残したテクストのしたたかさ、重厚な手ごたえを、私たちに納得させてくれるような註釈があり得ることもまた事実である。例えば『悪の花』所収の「交感」Correspondances と題するソネ、この作品には永い解釈の歴史がある。前半八行は当時(十九世紀中葉)一般に流布していた教義としての「照応理論」や美学としての「共感覚の理論」を、メッセージとして要約する構えをみせており、この点についての典拠研究は枚挙にいとまがない。けれどもこの作品が独創的であり得たのは、後半六行で具体的に四つの香りを列挙するに及んで、「精神と感覚の熱狂を歌う」ことへと力点を移すことによって、そのような理論的美学的メッセージの伝達ということからは大いに逸脱して、むしろ個別的なものへのこだわりへと横滑りしてゆくところにこそある。こういったことを文体論や統辞論の視点を踏まえながら、精緻に分析し論証してみせたのは、脱構築派の文学研究者ポール・ド・マンであった。この人の「抒情詩における擬人観と転義法」と題する論考は、「交感」というテクストが、テーマ、語彙、イメージ、比喩などにおいて、『悪の花』のもう一つのテクスト「脅迫観念」Obsession と明らかな連関を示している、ということを見事に証明してみせた。作者が表向きに標榜する構築的な世界が、内部から崩壊していく契機を見い出し、その細部にこだわって徹底的に論じわけるところに、新しい註釈の可能性が示唆されているのである。 詩の言語というものは、ある意味で学説や教義や物語、つまりは既成の言説によって流布される言葉の網の目が、実はいかに不備なものであり不完全なものであるのかを、私たちに自覚させるためにある、と言ってもいいのではないだろうか。言葉をあやつる詩人の営みは、世界に網を張って真理という獲物の到来を待つ蜘蛛のそれに似ている。そしてその蜘蛛の営みは、太古いらい人類が世界を認識しようとして不断に行なってきた試行錯誤そのものであろう。ド・マンが明らかにするように、ボードレールの仕業で興味深いのは、既成の認識論や美学を個性的な文体が見事に裏切っていく、その実態だろう。細部に宿る神を見出し、詩人にとっての思想はテクストの文目のなかにしかあり得ない、という事実を、あくまでもテクストそのものに即して浮かび上がらせることが、詩を語るという行為に与えられる積極的な意義である、と言っていいのかも知れない。詩のテクストと読者との間に註釈というものが介在する根拠を問われるならば、今はそのように答えるほかはない。 |