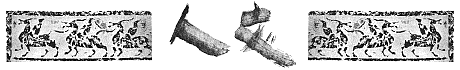
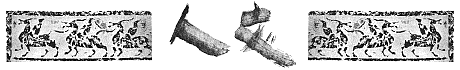
| 最新 | 講演会 | 研究所 | 研究活動 | 図書室 | 出版物 | アーカイブ | 目次 |
| 報告書 | 紀要 | 所報 | (第五三号 2006) |
| 随想 | 夏期講座 | 開所記念 | 退職記念 | 彙報 | 共同研究 | うちそと | 書いたもの | 目次 |
| 守岡知彦 | 岡田暁生 | 岡村秀典 |
| 人文科学研究所所報「人文」第五三号 2006年6月30日発行 | |
開所記念講演(2005年度) |
|
ピアニストになりたい! |
|
――練習曲の思想と一九世紀 |
|
岡 田 暁 生 |
|
|
バイエル、ツェルニー、クレメンティ、ハノン、ピシュナ等々 ― 言うまでもなく、ピアノ学習者必修の「練習曲」の数々だ。多くの人にとって「ピアノを学ぶ」とは、これらの練習曲をくる日もくる日も何時間もさらうことと、ほぼ同義のはずである。他のどんな楽器にも増してピアノは、練習曲というものと密接に結びついている。だが実は、こうした指のトレーニングのみを目的とする「練習曲」なるものが生まれたのは、一九世紀に入ってからのことである。ベートーヴェンやクレメンティの時代からピアノ演奏者に要求される技術難度が飛躍的に上がり、多くの曲に現れる難パターンを取り出して体系化し、効率的に学習者にマスターさせることを目的とする曲集が書かれるようになってきたのである。とりわけ一九世紀後半になると、もはや「曲」とすら言えない、指トレーニングのための純然たる「ドリル」が多く出版されるようになった。これはUbungとかExerciseと呼ばれるもので、ピアノ学習者なら誰でも知っているハノンなどがこれにあたる。 ハノンの序文には「この練習を最初から最後まで通して弾いても一時間半しかかかりません。これを毎日最初から終わりまで弾けば、やがてあなたの指はどんな曲でも弾けるようになっているでしょう」などという意味のことが書いてある。「ドリルを機械的にこなしていれば、自動的に、自動化された指(=自在に何でも弾ける指)が出来る」というわけである。実際一九世紀には多くのピアニストが、譜面台に楽譜の代わりに新聞などをのせ、それを読みながら、ひたすら一日に何時間も音階や分散和音や練習曲を次々にさらうということをやっていたらしい。一九世紀のピアノ学習者の多くは、いつか自分の指が新聞を読みながらでも曲を弾いてくれる自動機械になることを念じながら、日々ハノンのような指練習に励んだに違いない。 |
|
|
一九世紀の練習曲が「自動化された指」に託したもの、それは何よりまず、人間離れした「強さ」と「均質さ」であったと言えるだろう。一九世紀を通してピアノの鍵盤はどんどん重くなっていった。一八世紀までの鍵盤楽器はサロンのようなところで演奏される場合がほとんどだったので、「大きな音」などまったく必要とされなかったのに対し、一九世紀にはいると一〇〇〇人を超えるコンサートホールで弾くといった機会がどんどん増えるようになる。ピアノは一八世紀末までの木製の小さな箱から、鋼鉄フレームで支えられた巨大な黒塗りのメカへと変貌していった。一九世紀のピアニストの指に求められたのは、何より「耐久力」であり「大音量」であった。あれほど音楽の「精神性」を強調した一九世紀西洋が、いわば「(音楽史の)裏で」このような「マッチョな指崇拝」とでも言うべきものをはびこらせたことは、皮肉と言うほかない。だが、練習曲と指矯正器具で指を鍛え上げた多くの学習者たちが、何の疑問も感じずに、同じそのマッチョな指でもって、粛々とバッハやベートーヴェンやショパンを奏でていたであろうこと、これもまた否定できない事実なのである。 |
|
| 界面としてのキャラクター | 守岡 知彦 |
| 雲岡石窟寺の考古学研究 | 岡村秀典 |