|
死後,人間を含めたさまざまな存在に生まれ変わるという再生・転生の考えは,多くの文化に見られる。特にインド・ヨーロッパ諸語を話す諸民族は,古くからこの考えを共有していたようである。しかしインドにおいては,この観念は単なる民話や民間信仰のレベルを越えて,ほとんどすべての宗教や哲学の根幹を形成してきた。たとえば,仏教などで最高の目標とされる「解脱」は,終わることなく生死を繰り返す輪廻的なあり方からの解放にほかならない。インドの輪廻思想の特徴は,業理論(行為とその結果の必然的な結び付き)にもとづいた冷厳な論理と,再生のプロセスに関する一定のストーリーとを持っていることである。そのような輪廻説が成立する過程で論理とストーリーに枠組を提供したのは,ヴェーダ祭式をめぐって展開された古代インドの祭式思弁であった。
初期のヴェーダにすでに現われている祭式の効果(功徳)に関する思想と,祭式の最高の効果として天上界へ昇るという思想は,ヴェーダの後期になって思わぬ方向へ展開していった。この二つの思想がからみ合って,輪廻思想へと変質していったのである。祭式によって死後,天上の楽が得られるという「オプティミズム」が,その先にさらなる生死の繰り返しを見出すことによって,同じ再生への道筋に対して正反対の「ペシミズム」へと一変してしまったのである。祭式思弁の枠組の中でこのように形成された輪廻説は,ウパニシャッドにおいて祭式の文脈を離れて,人間存在そのもののあり方として説かれるようになる。そこでは輪廻の原因として,祭式行為に限定されない行為一般と,行為を起こす欲望とが問題とされるに至る。ヴェーダ祭式を否定する仏教が引き継いだのは,まさにこの,ヴェーダ祭式をめぐって形成され,ウパニシャッドで確立された輪廻思想であった。
|
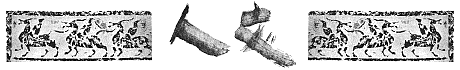
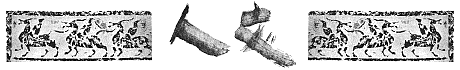

 の名物学
の名物学