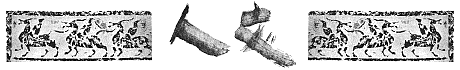
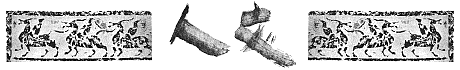
| 最新 | 講演会 | 研究所 | 研究活動 | 図書室 | 出版物 | アーカイブ | 目次 |
| 報告書 | 紀要 | 所報 | (第五三号 2006) |
| 随想 | 夏期講座 | 開所記念 | 退職記念 | 彙報 | 共同研究 | うちそと | 書いたもの | 目次 |
| 小林丈広 | 丸山 宏 | 高木博志 | 伊従 勉 |
| 人文科学研究所所報「人文」第五三号 2006年6月30日発行 | |
夏期講座(2005年度) |
|
都市の計画と京都の自己イメージの特徴 |
|
:明治・大正・昭和の三断面を通して |
|
伊 從 勉 |
|
|
都市を人間に例えると、都市の改造や計画という一種の治療行為は、都市の「身体的」病弊の治療や外科手術の意味にのみ受け取られ勝ちである。都市の組織には過去から現在に引き継がれる集合記憶や感情という心の働きが結びついているから、身体を物理的に改変すると、必然的に「心の不調」を引き起こす。絶えず身体をいじくっている都市という患者は、したがって、常に心を病んでいることになる。近代京都の心の病をここでは考えてみたい。 例えば、時代時代に流行った都市の自己イメージの掛け詞と当時の都市の身体状態とを比較することによって、心の病状を読み取ることができるはずである。その症状を医者が分析するだけでなく、患者自身が自分の身体と心の乖離を認め癒す努力を試みるところから、治癒への道が開けるかもしれない。近代京都が長く患ってきた心の病の代表的な症状のひとつが、「古都」であり「みやこ」という強迫観念的な自己イメージ、いいかえると近代化に直面した古都の自負の表現である。 今回は、明治・大正・昭和の三時期に登場した三つの近代京都の自己イメージの標語を例にして、京都というまちの都市の計画に纏る近代病の特徴を診断してみた。 |
|
| 第一章 明治中期の京都市民の白昼夢:「世界の公園 京都」 | |
|---|---|
|
明治一七年頃から始まる、京都府下の名所旧跡を「公園地」に指定する上申運動は、明治一九年許可の円山公園を例外として、ことごとく却下される。北垣国道府知事は、京都の名勝地を「京都固有の財源」とみて「名勝地の盛衰は即ち京都市の盛衰」と重要視し、なかでも東山一帯を「公園同様の姿」とみて、上地官林であった東山を円山公園に編入させる上申運動を始める。この方針は後の民選初の内貴甚三郎市長に引き継がれるが、明治三二年の国有林野下戻法の公布により、命脈を断たれる。 北垣時代の晩年の明治二四年、府議会から知事に出された建議書のなかに、山水明媚社寺輪換の旧帝都を「東洋の公園」と呼ぶレトリックが登場する。円山公園設置を含め、北垣の近代化路線を激しく批判した福沢諭吉でさえ、京都を「世界の遊園」と呼び、このレトリックが確立する。以後、「日本=世界の公園、京都=日本の公園」などのバージョンを伴いながら、「京都=世界の公園」説は、京洛名士の常套句となる。 重要なことは、この種のプライドを含む自己イメージには、ある種のコンプレックスが同居していることである。近代都市として必要な都市施設の公園を、在来の名所旧跡として理解した明治の名士・地方役人・地方インテリ層の誤解が一方にある。その都市施設の公園を設置できなくても、もともと京都は「公園(名所旧跡)」であるという意識には、官林の公園化に失敗した京都人の「自負」が込められている。 |
|
| 第二章 公園のない「公園都市」:都市計画の導入と苦しい自己イメージ | |
|
一九一九年になって、政府は初めて都市計画法と市街地建築物法を公布し、東京以外の都市の近代化に本腰を入れ始める。当然、営造物である都市施設として必要な公園設置の要求は高まる。一九一七年に市域を六○平方キロメートルに拡大した京都には、府立公園を含めわずか四ヶ所の公園、市民一人当りにしてわずか○・四平方メートルの公園施設が設置されたのみであった。 内務省都市計画局が一九二二年に監修した「京都都市計画」(長期計画)の概要の公園の項目には、全市を公園と見なし公園設置を無用と見なす、過去の京都礼賛論を批判する条がある。社寺の境内を代用公園と見なすことは、「現代及び将来に適合したる近代的休養地」を必要とみる都市計画的視点からは、不十分であるというのである。 ところが、この計画策定に先立ち、内務省の都市計画課課長から都市計画区域設定の照会を一九一八年に受けた京都市工務課長は、次のようなやり取りの記録を残していた。すなわち、山紫水明名勝旧跡に富む「我が京都」は「日本の大公園」であると胸を張り、都市計画区域を指定する際、京都盆地東北西を住居地域に設定することで、公園都市の性格を保持できると答えている。事実、一九二二年に指定された「京都都市計画区域」(九二平方哩)の設定理由書には、「公園都市たるの特徴を益々発揮せしむる」ため、都市計画区域の四○%を占める山地を区域に編入した、と述べているのである。 この当時、都市計画の執行は、環状道路計画と市中縦断道路の路線設定問題で、町中がひっくりかえるほどの激論の最中であり、公園どころの話ではなかった。その証拠に都市計画公園第一号の船岡山公園の計画決定は一九三二年、開園は一九三五年までまたなければならない。都市計画区域の山地が営造物の公園を代用する傾向は、明治以来依然として昭和の「大京都」にも引き継がれたのである。 一九一八年から一九三○年代の京都に流行った「公園都市」標語は、まさに、公園のない「公園都市」のレトリックであった。まちの近代化に直面して明治の京都人が抱いた「自負」の発奮が、姿を変えて昭和の大京都にも登場している。 |
|
| 第三章 文化財都市・京都を米軍が救ったのか:敗戦後の国際文化観光都市の起源とウォーナー伝説 | |
|
太平洋戦争末期の日本都市への原爆投下作戦の進展と、投下都市の選定過程において京都が常に有力候補に位置づけられていた事情については、一九七○年代のオーティス・ケリー氏、一九八○年代の鈴木良氏、一九九○年代には吉田守男氏、そして米国の軍事資料を広範に渉猟したアルペロビッツ氏の研究により、ほぼ明らかにされている。 一九四五年七月のポツダム会談のさなかに至るまで、米国陸軍の航空部隊は、京都を原爆投下の最有力都市のひとつに温存しており、原爆の物理的効果を測定するため、京都を通常爆撃の対象から外していた。そのため、京都は小規模の限定的空襲を四五年の一月と六月の二度被るに留まった。 ところが、原爆投下のため通常破壊が担保されたことを知らずにいた日本に、敗戦後、世界的に重要な文化財都市を、文化財保護を理由に米軍が破壊から救ったとする伝説が、奈良や京都そして鎌倉が生き残ったことの解釈として生まれる。その事実経過を解明した吉田守男氏の調査に依れば、その伝説の発端は、一九四五年一一月の朝日新聞の記事であった。 記事に登場する、ハーバード大学付属フォッグ美術館東洋部長「ラングドン・ウォーナー」(ママ)氏が、伝説の起点であった。ウォーナーが一九四四年四月以降に中心メンバーとなって作成した「戦争地域における美術的歴史的遺跡の保護・救済に関するアメリカ委員会」の文化財リストの真相は、戦争中の文化財保護を目的とするよりは、休戦時に、「枢軸国の博物館やその指導者の私的コレクションのなかから被侵略国に引き渡されるべき[損害に対する返済用の]等価値の美術品・歴史的公文書のリスト」であることを、吉田氏は明らかにした。しかし、当時この真相を知らずにいた美術評論家矢代幸男氏は、ウォーナーと三十年来の仲であったため、ウォーナーが軍部に影響力を行使し、爆撃を抑止したとの説を記事で述べた。この憶測が誤解とは知られることなく、瞬く間に、ウォーナー救済伝説として日本中を駈け抜けることとなった。その結果は驚くべきブームとなって、戦後史に跡を残すこととなった(詳細は吉田氏の著作を参照)。日本政府は、一九五五年のウォーナーの死の直後、勲二等瑞宝章を授与し、同年、高山義三京都市長もハーバード大学に爆撃抑止に対する感謝状を贈っているほどである。 驚いたことに、この伝説は戦後の京都イメージの起点になっている。一九五○年一一月に公布される「京都国際文化観光都市建設法」は、その発想の原点に、「京都は、日本文化の象徴であり、爆撃の目標から特に除外された世界平和の生きた記念像である。」という認識を置いている。爆撃目標からの除外が原爆の投下目標であった事実を知ることなく、京都の文化財が「国際的」である保証を、敗戦後日本中を駈け抜けたウォーナー伝説から得ていたのである。 この法律が京都の有力国会議員を中心とする議員立法であったことは、興味深い。当時、立て続けに立法されていた非戦災特定都市の復興法制度に乗り遅れまいとした京都の名士たちは、今となってみれば誤解に基づく爆撃除外の「国際文化観光都市」という政府が用意した都市イメージを、戦後の京都イメージに選び取ったのである。 |
|
|
こうして、明治・大正・昭和の三断面を通じて、京都の自己イメージの発現に共通する性格が認められることが分かる。外部からやってくる近代化や開発などの圧力に対し、その都度発現する、この歴史都市の「自負」表現の深層心理的特徴である。 |
|
| (2006.4.13脱稿) | |
| 京都史の文法 | 小林 丈広 |
| 近代京都名勝考 |
丸山 宏 |
| 近代京都と国風文化・安土桃山文化 | 高木 博志 |