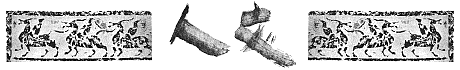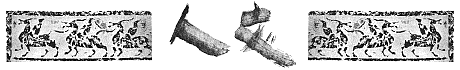|
三教交渉の研究班で会読をすすめているのは唐の神清の撰『北山録』十巻。その文体にはなんとも妙なところあり,先行文献の文章を殆どそのまま引き写して自らの文とするようなこともまま見られる。人のフンドシで相撲を取るばかりか,フンドシを次から次へと取り替えるその手口に独自の妙味があるようなものだ。読み手である我々は,もとづく資料を同定するため漢文仏典の渉猟を余儀なくされる。その関連で最近個人的に面白いと思ったのは,些細な事といえばそれまでだが,唐代の仏教説話集として知られる『釈門自鏡録』と本書の関係である。本書の成立は八世紀末か九世紀初め頃。一方『釈門自鏡録』の編纂年代は諸説あるが,近年の研究によれば八世紀初め頃という。つまり恐らくは『釈門自鏡録』が先,『北山録』が後なのであって,その両者だけにみられる話や,ある話から別な話に移る順序(フンドシの取り替え方)が一致する事例が数カ所あるのだ。普通にアタリをつけて出典調べするなら,『北山録』の典拠として『釈門自鏡録』をひもとく者は多くあるまい――『釈門自鏡録』は殆ど他の伝記を抜粋しただけの書物なのだから。白状すると,注目のきっかけとなったのはパソコン検索であった。闇雲な検索にも時としてメリットはあるものだ。
話は飛ぶけれども,パソコン依存度の年ごとの増大は漢文仏典を読む者にもあてはまる。インド学チベット学の方では,データ入力や検索は十年程前から行なわれている。サンスクリットやチベット語は表意文字であり,研究上欧米との関係が緊密なこともあって,キーボードになじむのである。またこう言うと語弊もあろうが,日本のインド学は大半を仏教学者が占め,その多くが寺の出身であり,坊主にはメカ好き,新しもの好き,そして金のかかること好きが多い。この点からもインド学における速やかなる電子化は三段論法風に言える。他方,漢文仏典の場合はどうかといえば,少し様子が違って,昨年二〇〇〇年あたりが,一部専門家を除く一般の末端ユーザ研究者の間で漢文仏典の語句検索が普及し始めた年だったのではないか。さて,電子テキストが良くも悪くも使いかた次第なのは言うまでもない。研究の量や作業の速度はともかく,コンピュータの使用自体が研究に質的向上をもたらすわけではない。今も昔も事態は本質的には変わっていないし,今後も変わらないだろう。大切なのは普段の読書,それだけだ。しかしである。本を何度もひっくり返し,時には寄り道して思いがけない資料に出会ったりしながら,やっと典拠がわかったときの喜びと小さな達成感,効率の悪さがもたらす豊かさ――それにひきかえ検索をかけて出典を知ったときのあっけなさといったら! 肉体感覚の欠如した知識とでも言おうか。もし失うものがあるとしたら,その損失,すこし大きすぎることはないだろうか。
|