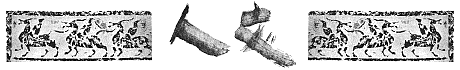
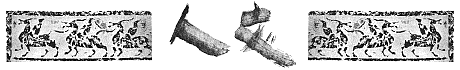
| 最新 | 講演会 | 研究所 | 研究活動 | 図書室 | 出版物 | アーカイブ | 目次 |
| 報告書 | 紀要 | 所報 | (第五三号 2006) |
| 随想 | 夏期講座 | 開所記念 | 退職記念 | 彙報 | 共同研究 | うちそと | 書いたもの | 目次 |
| 冨谷至 | 岩城卓二 | 王寺賢太 | 古松崇志 | 原田禹雄 |
| 人文科学研究所所報「人文」第五三号 2006年6月30日発行 | |
所のうち・そと |
|
晴れた日の朝には自転車で |
|
王 寺 賢 太 |
|
|
晴れた日の朝には自転車で、私は下鴨の三角州を駆け抜けて行く。ある時には下鴨神社の本殿のそばから参道沿いの側道に入って、出町柳のほうからゆっくり歩いて来る参拝客とはちょうど逆向きに糾の森を突っ切って行く。原生林というには少し気がひけるが、人手の入ったことがないのは事実であるらしい広葉樹の繁みから朝日が差し込んで来る。その光が周囲に散乱するのを感じながら、ただひたすら無心に自転車を漕いで行く。夏には緑色に染まる光線が、晩秋に深々と色づいた紅葉を透かして森の中の地面のそこここに赤い影を落とす時には、ふと足を止めてそれに見入ってしまってもいいだろう。またある時には出雲路橋から賀茂川のほとりに出て、川沿いに堰堤を駆けて行く。人家の立ち並ぶ通りを抜けるといきなり、広々とした高い空と街の外郭の山々の連なりに縁取られたのどかな風景が開ける。冬枯れの貧寒とした岸辺が一気にはなやいで、春になれば桜、菜の花、青草に次々に彩られるその風景の真ん中を、まっすぐに貫いて走って行く。空には鳩、鴉、あるいは鳶。雨の後で流れが激しくなってさえいなければ、水面には白鷺や鴨の親子。「かもがわ」という名のこの川に実際に鴨が泳いでいるのを目にすることになるとは、少し前までの私は想像することさえなかったのだが。 人文研に到着して一年有余、自宅から研究所までの「自転車通学」は、すっかり私の日常となってしまった。糾の森にしても、賀茂川の堰堤にしても、とりたてて大きな空間ではない。そこを自転車で駆け抜けて行くのも、せいぜい五分程のことにすぎないだろう。しかしそのつかの間の経験は、いつもかすかな驚きとささやかな喜びを私に与えてくれる。地方都市とは言え百五十万もの人が住む京都の街の中に、穿たれた穴のように残された自然。人為によって飼い馴らされてしまったわけでもなく、かといって人間を圧倒するでもない、あくまでも穏やかなその広がりと絶え間のない変化。とは言えその穏やかさは、包み込んでくるような優しさであるよりも、むしろ親密さも敵意も欠いた無関心のようなものだ。その穏やかな無関心の中を通り過ぎるたび、私は不意に、ほとんど懐かしさとでも言いたいような感情にとらわれる。 |
|
|
幼少を過ごした九州では時々近くの山や川に出かけて遊んではいたが、所詮は工業都市の子にすぎないし、物心がついてからは九州から東京へ、東京からフランスへ、そしてそれぞれの土地であちらからこちらへと引っ越しばかり繰り返してきた私が、下鴨の森や川のほとりで突然懐かしさらしき感情に目覚めるというのもいささか滑稽な話ではある。しかし長年の外国生活の後、京都で家庭を持ち、大学に職を得ることになった私が、自宅から職場への行路の途上に開けたささやかな自然の中で、何がしかの感慨に襲われるというのも理由のないことではなさそうだ。それを自然と呼ぶとしても、そこで問題になっているのはあれこれの場所や風景ではなくて、むしろ自分自身を取り巻く関係の網の目の中に開いたある種の空隙なのかもしれない。そして、そこでとらわれる感慨を懐かしさと呼ぶとしても、それはもはや過ぎ去ってしまった過去への感傷とは似て非なるもので、むしろさまざまな関係の手前にいまだつねに居残り続けている私自身と、つまり何者でもない誰かと、再び遭遇する時に覚える感情なのかもしれない。 明日の朝もまた、天気さえ良ければ、私は自転車で下鴨の三角州を走り抜けて行く。行き違う周囲の風景に目を楽しませ、風と光を突き抜けて。ただ、不用意にペダルを漕ぐ足を止めてしまわないように気をつけながら。 |
|
| つまらなかったNHK「新シルクロード」 | 冨谷 至 |
| 小中学校教員を養成すること | 岩城 卓二 |
| 二○○三年春北京にて | 古松 崇志 |
| 奨励賞を受けて | 原田 禹雄 |