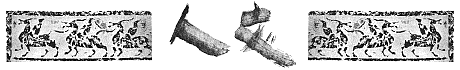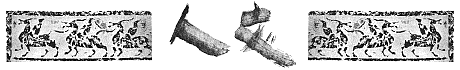| 人文科学研究所所報「人文」第四六号 1999年11月18日発行 |
|
《座談会》人文回顧(II)――二一世紀を展望して |
大浦康介/籠谷直人/金文京/小山哲/阪上孝
/武田時昌/冨谷至/横山俊夫/吉川忠夫 |
|
<旧館から新館へ> |
| 武田 |
それでは座談会を始めます。本誌では,一九七五年に新館落成記念として座談会を行ったことがあるので,パートⅡということになります。今日は,それから今に至る約二五年間を回顧したいと思います。ただし,一回目は,御年配の先生方が創立以来の思い出を話されたのですが,今回は過去を振り返りつつ,まもなく訪れる二一世紀のことを展望しようという趣旨で,世代横断的に集まっていただきました。まず所長を務められた吉川・阪上両先生にこれまでの歴史的な流れを概略的に語っていただきながら,人文研の将来像についての意見を自由に交換したいと思います。 |
| 阪上 |
日本部と西洋部については,本館が建った前と後では,ずいぶん違うと思います。二階建てだった旧館の時は,外観は美しいけれども,内部は難儀な建物でした。戦後すぐの頃にアメリカ軍に接収されていたなごりか,本棚にハワイの椰子の絵があったりして,最初に助手で来たときは妙なところだなあというのが印象でした。 |
| 横山 |
私も旧館に住んでいた一人ですが,裏に石炭部屋とかいう一室があり,お化けが出るとか,地下に進駐軍が埋めた女の骨があるとかの噂があったところを見つけ出し,自分で片づけて勉強していました。 |
| 吉川 |
私がここに来たのは七四年でしたが,出入りは大学院の頃からです。当時は,ここの共同研究班が大学院の授業の代わりになっていたものもあったんですよ。例えば雍正批諭旨がそうでした。 |
| 阪上 |
旧館時代は,助手が二人相部屋だった。建物の西北に談話室と宿直室があって,お茶を呑むとか,電話をかけるのにはそこにいかないとだめだったから,いろんな人としゃべる機会があった。新館ができて,雰囲気はずい分変わりましたね。 |
| 横山 |
建物ができて,いよいよ部屋割りという会議で,そばにいた藤枝晃さんがプランを見て,こりゃあかんで,みんな四畳半趣味になるがなと耳打ちされた。大部屋でワイワイやるのが,人文のスタイルだったんでしょう。 |
| 冨谷 |
東方部は今でも相部屋ですよ。雰囲気はだいぶ違っているでしょうけど。 |
| 阪上 |
何々研究室とかでしょ。東一条では,分野の違う者同士が同室になる。私は飛鳥井雅道さん,法学部からこられた横山さんは確かシュメール学の前川和也さんと同室だった。 |
| 吉川 |
東方部も歴史研究室と言っても,住人は別のこともある。 |
| 冨谷 |
そういえば,私は宗教学研究室でインド学の赤松明彦さんと一緒でした。 |
| 小山 |
この特集号にいただいた原稿でも,相部屋の話があって,しかも勉強したという話があまり出てこなくて,ほとんど遊んだ話ばかりなんですよ。 |
| 横山 |
梅棹忠夫さんに聞いたら,研究所に行くと,朝から晩までほんまによくしゃべったと言ってられた。 |
| 阪上 |
同室だった飛鳥井さんから,コミンテルンとかの話を聞かされて,おのずと耳学問ができた。 |
| 冨谷 |
突然にガラッと外部の先輩の先生がやって来られて,そして長時間そこにおられ,私にははなはだ迷惑,ということもありました(笑)。 |
| 大浦 |
でも,そういうことのできる雰囲気のある開かれた場所だったんでしょう。 |
| 金 |
人文の助手はそれでも文学部にくらべれば,恵まれているでしょう。文学部は,雑用が多くて大変でした。 |
| 阪上 |
よしあしもあるということでしょう。ずっと居座られて,相手をしないといけないのもかなわないけれど,新しい知見も得られることもある。 |
| 籠谷 |
今は少し静かすぎますね。雑談するスペースは確かにない。 |
| 金 |
東方部のロビーなんかも,広いスペースに誰もいなくてもったいないと今日話してたんです。 |
| 横山 |
普段あちこちで雑談するというのは,案外大事なことです。会話がないと,よけいな誤解も生じることだし,将来構想なんかも雑談レベルでもっとやらないといかんね。 |
| 大浦 |
七五年の建物の変化が研究者自身のあり方や相互関係の変化と対応しているということでしょうか。 |
| 阪上 |
それは,あるでしょう。残念ながら左翼の力がどんどん落ちてきましたね(笑)。進歩的文化人がリードしてきた総合雑誌が注目されなくなり,論壇の力が衰えてきたことも大きいでしょう。日本全体の変化の現れですね。 |
| 大浦 |
以前は皆がいくつかのテーマを共有していて,それで議論がはずんだ。数の限られた大きな話題,共通の関心事や問題意識があったように思います。ところが,情報が溢れ,知識が細分化されるようになって,かえって議論への情熱は薄らいだのではないでしょうか。 |
| 金 |
確かにその通りだけれども,例えば旅行に行っても宿屋に一緒に泊まらなくなって個室になったでしょう。暮らし向きの違いだと,私には感じられます。 |
| 阪上 |
僕が助手になったのは六六年ですが,当時は給料も安かったですね。だから,研究会の後の二次会は,面白い話が聞けるうえに,ただ酒が飲めて大変うれしかった(笑)。それに,助手仲間で安い酒場でしょっちゅう呑んだくれて,わいわい騒いでましたね。七〇年代以降は,豊かになったのと,個人主義が強まってきて,そういう風潮は少なくなってきたのではないでしょうか。 |
| 横山 |
そうした変化というのは,日本だけではなく,世界的にも見られます。 |
| 籠谷 |
七五年くらいから今に至るまで連続する何かがあるように思えます。私は,その後退期に勉強をはじめたわけだけれども。 |
| 大浦 |
その変化をできれば,ネガティブに捉えるのではなく,未来志向で考えたいですね。 |
| 武田 |
共同研究にふさわしいテーマが見つかったところで,そろそろ次の話題に。 |
|
| 旧館から新館へ |
| 大学変革の動きのなかで |
| 共同研究のタイプ分け |
| ポスト共同研究の試み |