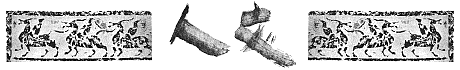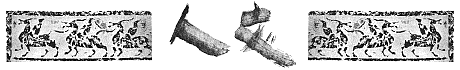|
共同研究班『訳経僧伝研究』は班長の定年退官とともに二〇〇一年度一杯で終わりを迎えた。桑山教授が
行歴僧,訳経僧の伝記を研究する一連の研究班をスタートさせたのは一九八三年のことだから,まる十九年
続いたことになる。私が参加するようになったのは確か一九八七年,『大唐大慈恩寺三蔵法師伝』の会読の
最後の方だった。その後,『慧超往五天竺国伝』,『悟空行紀』,『法顕伝』,『高僧伝』と会読を続け,訳注や索引
を作成してきた。これら中国,インド,中央アジアといった地域を経巡った僧侶達の記録は,このところ国際政治
のホットスポットとなっているアフガニスタンあたりの歴史地理を考究するためにも欠くべからざる資料となっている。
ところでアフガニスタンについては前々から気になっていることがある。それは「カブール」という,昨年来数え
切れないほどメディアに登場している言葉だ。もちろんこれはアフガニスタンの首都「カーブル」のことなのだが,
以前から日本のメディアはこのまちを「カブール」と呼んでいる。外国語の発音を日本語で正確に写すのは困難
な場合が多く,この呼称の使用自体に目くじらをたてるつもりはそれほどないのだが,それにしてもなぜ「カブール」
と呼ぶのか,その由来来歴は気になる。これまではぼんやりとフランス語の Caboul あたりがもとなのかなと思っ
ていたのだが,昨年末に国立公文書館のウェブ・ページに開設された「アジア歴史資料センター」で昔の外交文書
を検索できることを知り,試しに調べてみた。そこで見つかった最も古い記録は明治一八年(一八八五年)の「亜富
汗論近況ノ件其二」と題する文書だった。これは当時のアフガニスタンにおける英露の紛争に関する在露特命全権
公使花房義質からの報告で,そこに「カブール」という言葉が見える。ところでこの報告,ロシアから送られてきた
わけだが,ロシア語では「カーブル」は Rfaeek と書かれる。力点はeの上にあるようだからこれは「カブール」に近い
発音なのだろう。ということは日本における「カブール」という表記のもとはロシア語の発音だったのではないか。と,
勝手に納得しかけたのだが,念のためもう少し遡って江戸末期,万延元年(一八六〇年)に翻訳された地理書『地球
説略』をパラパラめくってみた。すると「加布利」と書いて「カブユル」とルビを振ってある。またに徐継畭の『瀛環
志略』に井上春洋らが訓点したもの(文久元年/一八六一年)では「喀布爾」に「カビユル」とルビを振ってあって,
なんだかよくわからなくなってしまった。この調べものはもう少し先がありそうである。
ちなみに研究班で会読してきた僧伝には,不思議なことに「カーブル」にあたりそうな地名は出てこない。かつて
研究班で班長からその点を示唆されたことが,この地域の歴史地理を考える上で大きな鍵となった。私が研究班
から受けた数多くの恩恵の一つである。
|