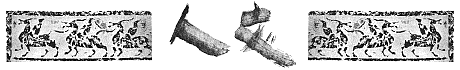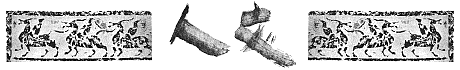|
数年前にコレージュ・ド・フランスで開催された,進化論や古生物学・地質学の歴史にかんする連続講義でのこと
。回を重ねて出席するなかで,私はある日本人の男性と知り合いになる。何回目かの講義の後,最初どちらからと
もなく話しかけ,簡単な自己紹介から始まり,程なくカフェに場所を移して話を続けた。聞けば彼は東京のメーカー
で働いていたが,十年ほど勤務した後その仕事を辞め,パリにやって来て視聴覚の障害者教育にかんする研究を
はじめたのだという。そのころ私もたまたま,第三共和政期における精神遅滞児の教育政策についての文書などを
読んでいたところだったから,その方面で話が一山咲く。ややあって私は「ところで,どうして進化論の歴史に興味
をおもちなんですか」と切り出した。そのとき一瞬,彼の眼がキラリと輝くのに気づいたとき,私は「ああ,しまった」と
後悔の念を抱く。人の話を聞くことはけっしてキライではないのだが,そのときは後に別の待ち合わせが控えていた
のだ。案の定,彼の方は「いや,進化論の歴史はさておき,私自身,〈私の〉進化論というのを考えていましてね」。
そして彼が自分で構想したという,無機物から始まり有機物へと連なっていく壮大なヴィジョンは,時計にチラチラと
目をやる私の前で,優に一時間は続いたのだった……。
進化論とは気の遠くなるような時間のスパンのなかで,生物の多様な広がりと変化を説明する理論である。大きな
スケールの時空間のなかで生起する因果律を含むわけだから,それはまさに一つの世界観を構成する。進化論の
歴史をみれば,それがいかに既存の宗教に抵触してきたかがよく分かるだろう。そしてそれは過去の話でなく,現在
においてもなお紛糾した議論をよぶ主題なのだ。こうしたトピックが「私」という一人称のもとで語られることは,一見
やや奇妙にみえる。しかし私がパリで出会った男性が,特に変人だったわけではない。フランスから帰国して共同
研究「進化論と社会」に加わったとき,私はときとして彼のことを思い出した。というのも,彼を彷彿とさせるような語
りに,研究会のなかで何度となく出くわしたからである。もちろん,それぞれ専門を定めた研究者たちは慎重だから,
軽々しく「私の進化論」などとは口にしない。それでも,経済学や社会学,歴史といった専門を越え,ヨーロッパや
アジア,アメリカという対象地域も越え,自然科学と人文・社会科学という枠すら越えて,饒舌な語りが流れていく。
そして周りの者もあるときはそれに魅せられ,あるときにはやや辟易しつつも,後の議論はきまって白熱するのだった。
あるいはむしろ,一種の世界観であり壮大な視野をもたらすからこそ,かえってそこに世界と相対する一個の「私」
が出現するのかもしれない。そのようないわば進化論をめぐる「私」の現象学を考えても,おもしろいのかもしれない。
しかしかくいう私も,数年前まではほとんど興味を寄せることのなかった進化論なのに,いつの間にか関連資料は
書棚のなかを増殖していき,ときには長い間この対象に取り組んできた専門家のような口振りをすることさえある。
「私の進化論」を口走るときだって,近いのかもしれない。それはともかく,この共同研究も本年度で終わり,近い内
に報告書が出る。おそらく読者はそこに,複数の「私」の影を見いだすことだろう。
|